登場人物の増やし方と連結方法

いつも創作お疲れ様です。
今回は、物語に登場するキャラクター、すなわち登場人物。そしてその増やし方と連結方法について解説していきます。
作家であるあなたは、サクサク増やしたり、連結しているかと存知ていますが、ややもすると混乱しがちです。そこで、ポイントをいくつか抑えておくと物語が作りやすくなる考え方をご紹介していきます。

キャラクターの種類
キャラクターの種類は、カテゴリ別に分けると、主人公・ヒロイン・ラスボスを中心とするメインキャラクターと、それを支えたり、盛り上げるサブキャラクターです。ついでに、盛り上げるサブキャラクターの内、物語を進行させるための力がないキャラを脇役と呼びます。
つまり
①メインキャラ(主人公・ヒロイン・ラスボス)
②サブキャラ(メインキャラ以外で物語を進行させる人物)
③脇役(サブキャラ以外で物語と関係しない人物)
あっさりしていますが、はい。実はこれだけなんです。
でも、メインキャラの中に、ヒロインなら、まだしも、ラスボスが存在してますが、ちょっと気になりませんか?
実は、このラスボスという登場人物ですが、主人公と対極にあるから主役レベルなんですよ。
そもそも、ラスボスという言葉なんですけど、特にRPGゲームで登場する最終決戦する対象という意味ではなく、このブログでは、あなたの理想的な自分を否定する意思の化身として定義してます。
関連記事:ラスボスとは何か?
次に、メインキャラを盛り上げるために存在するサブキャラクターについてです。メインキャラだけが物語を展開させても、やっぱり面白くありません。サブキャラクターが絡んで盛り上がります。
このサブキャラクターの意味は、〝脇役〟という意味ですが、ボクが思うに、メインキャラと同じ存在感を持ちます。
でも、サブキャラクターの増やしすぎはよくないんですよ。なぜなら物語が崩壊したり、設計しずらくなるので要注意です。詳しくは後述いたしますね。
そして、主役を支えるサブキャラクターの代表格が、ヒロインです。
このヒロインは基本的に、主人公を直接支えるキャラクターです。ヒロインはサブキャラとは別格な存在ということを覚えておいてください。
ヒロインと関係しているのがサブキャラクターであり、ヒロインを通して主人公を後押しするのが基本です。(もちろん、主人公と直接関係しているのもあります)
〝キャラクター〟と聞けば、個性の強い人物というイメージがありますが、キャラクターは〝性格〟という意味です。
実は、性格には、ざっくり4タイプあります。詳しく知りたい方は下の記事をご覧ください。
関連記事:性格4種とキャラバリエーション
キャラの増やし方

メインキャラクター(主人公・ヒロイン・ラスボス)3名のキャラを、ボクは〝固定キャラ〟と呼んでおります。
なぜ〝固定〟か?というと、結末までブレることはないからです。その固定キャラに、どんどんサブキャラや脇役を下にくっつけていくわけですが、
そのサブキャラクターの数は、主人公の目的や使命の大きさによって異なりますので、具体的に何人にしなきゃいけないというのは、申し上げられません。
強いて言えば、サブキャラクターは、少なければ少ないほど、物語がスリムになる、または可読性が高くなるということです。
特に、主人公に直近でくっついているのは、ヒロインの他に〝身内〟が挙げられます。
また、ヒロインにも、〝友人〟など、サブキャラがくっついています。
ラスボスにも、サブキャラがくっついており、一つの物語につき、最低5~6人の登場人物が、一番スリムな形となります。
と言いましても、舞台設定(世界)が、複雑だったり、スポ根ジャンルではチームで試合をするので、敵、味方を合わせると、5~6人では収まりません。
脇役はおまけ程度なので、プラス1~2人追加すると、8人くらいが妥当な数かと思います。
関連記事:舞台設定
サブキャラの連結の方法

サブキャラクターとは、メインキャラクターを支えたり、足をひっぱったりする存在です。
あなたは、今手漕ぎボートを漕いでいます。するとボートの底に〝穴〟があいてます。急いで穴を塞ぐと、今度は別の穴があいて・・・といったイメージで、
つまり、協力したり、敵対したり、物事がスムーズにいかず、やや複雑なドラマ曲線を起こすのが、サブキャラクターだと言えるでしょう。
関連記事:物語はドラマ曲線を描く
サブキャラを連結する、とは何かというと、メインキャラクター(主役)との〝関係性〟と〝立場〟を決めていくことです。
登場人物の増やし方と同じく、メインキャラクターの周囲にいるキャラをイメージしつつ、確実に必要なキャラ以外は削除をするといった消去法となります。
〝関係性〟とは、
身内か?、他人か?であり、
〝立場〟とは、
上下関係です。それが明確にならない内は、物語の設計図がみえずらくなるので、メインキャラクターと位置づけせず、頭の中でニュートラルな状態でいることをおすすめします。
メインキャラクター(主役)と連結する際に、一番大切なことは、そのサブキャラクターに、〝物語に必要な役割〟を与えることです。
物語がジグゾーパズルだと考えてみましょう。そのたった1つのピース〝役割〟が足りないとゲーム(物語)は完成しせん。
はい。ということは、そのサブキャラの存在は、必然的にメインキャラクターと出会わなくてはいけませんよね。
当然、その物語に、主人公と(いつ、どこで)運命的に〝出会い〟という設定が必要になります。
いかがでしたでしょうか?次回は、サブキャラの関係性と立場の作り方についてです。お楽しみに!
あなたの創作を応援してます。
以下は、登場人物の増やし方と連結方法をまとめました。こちらもご覧くださいね。
(1)登場人物の増やし方と連結方法←今ここ
(2)サブキャラに派閥をつくる
(3)脇役の増やし方
関連記事:サブキャラの関係性と立場の作り方








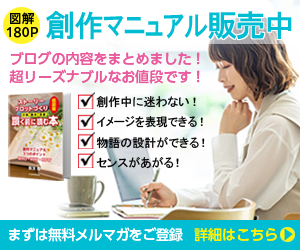
最近のコメント