ラスボスとは何か?

いつも創作お疲れ様です。
本日は、必ずといってよいほど物語に登場する人物〝ラスボス〟について解説します。
少し余談ですが、組織の頂点にいるボスがラスボスに見せかけて、実はその配下(参謀)が最後の敵となる場合があります。それを裏ボスと呼ばれています。
物語って、やっぱり〝結末〟がありますよね?
〝結末〟の一歩手前には、主人公のゴールやミッション(使命)の行方がどうなるか否かハラハラドキドキするシーンって必ずあります。
関連記事:ハラハラドキドキの出し方
主人公が、目的(ゴール)を定め、スタートしてから、紆余曲折を経て、やっとのことで願いが叶う最終地点。。。
そこに立ちはだかるのが〝ラスボス〟という存在です。
実は、はじめから仲間が裏切っていた・・・なんていうどんでん返しもアリなんです。
つまり、ラスボスとの戦いの結果(勝敗、YesかNoなど)のイベントです。
主人公の内なる葛藤や、外敵と呼ばれる対立シーンが、ファイナルステージに配置されています。
関連記事:2つのラスボス
よーいドン!で、物語のアクション・フラグ(旗)が立つ、ということは、当然、フラグも下がるように、主人公の目的を中心としてスタートした物語も、必ず終わり(ゴール)がやってきます。
主人公が、難しい問題を解決したり、つっかかっていた壁を解消して、誰もできなかったことが達成できた後、幕が下りるワケです。
読者さんたちも、その姿に手の平に汗をかきながら、熱い眼差しで見張っていますよね。
つまるところ、ラスボスという登場人物は、その主人公のゴールやミッション(使命)を、最終的に邪魔や妨害をする存在なんですよ。
ニュアンス的には、Weblio辞典で表記されている、ラスボス感に近いです。バトルもので言えば、敵(かたき)であり、恋愛ドラマで言えば、恋敵(こいがたき)です。
必ず、最後(ラスト)にこの人物が登場します。スターウォーズで言えば、暗黒卿のシスですね。
創作前の3つの決め事の内①誰?は、あなた自身の弱さの象徴でもあると申し上げました。強いて言えば、あなた自身の内面にある、理想や希望にド反対する超強力な意思力を持つ存在です。
以上、ラスボスとは何か?についてご紹介させていただきました。
あなたの創作を応援しています。
関連記事:悪役は〝悪〟ではなく人間の弱さの演出




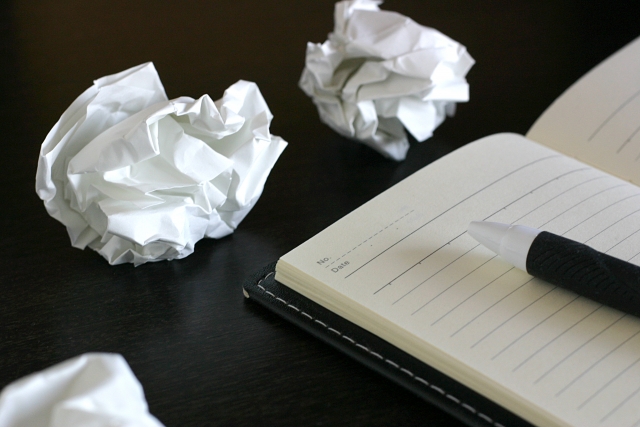



最近のコメント